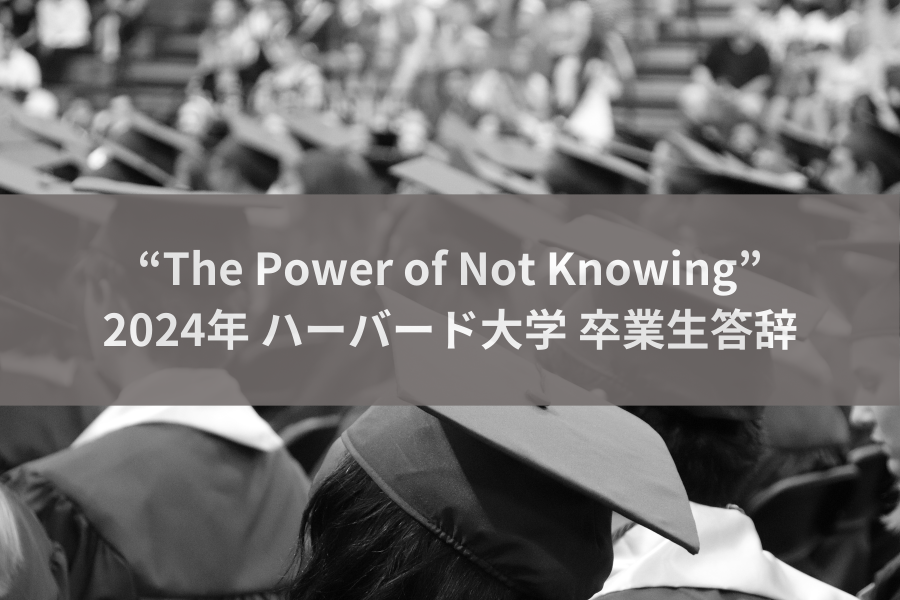かなり話題になっていたので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。2024年のハーバード大学の卒業式における、Shruthi Kumar(シュルティ・クマール)さんの答辞です。恥ずかしながら、僕がこのスピーチを知ったのは2025年になってからでした。「ハーバード大学の卒業生答辞かぁ。アメリカ人だから、ウィットに富んだおしゃれなスピーチなのかな」なんて感じで気軽に見始めたのですが、いやはや、すごいものを見てしまいました。価値観を揺さぶられるというのは、こういうことなのですね。スピーチのテーマは“The Power of Not Knowing”というタイトルの通り、直訳すると「知らないことの力」です。彼女が大学生活を通じて直面した困難な出来事の数々を軸に話が展開され、「アメリカって、そんな大変なことになってるのか…」と驚き、そんなことも知らずに暮らしていた自分を恥じつつ、12分弱という時間で価値観を覆されました。彼女が語っているのは、不確実な世界の歩き方です。スピーチの背景にあるいくつかの出来事について自分なりに調べたことも含めて(これがわかると、スピーチの意図がよくわかります)、感じたことを書き残しておきたいと思います。
まずは動画をご覧ください。
この動画をつくってくださったVox Novaさんに心から感謝します。英語と日本語訳が字幕で併記されており、英語が苦手な僕は大変ありがたかったです。一度目は日本語字幕を見ながら全体の意味を理解し、二度目からは英語の字幕を見ながらクマールさん自身の英語のリズムで視聴すると、彼女の心の動きが迫力をもって伝わってきます。一方的に話すのではなく、聴衆のリアクションを見ながら、気持ちのキャッチボールをしている感じ。ひとりのスピーカーが、会場の空気を支配していく様子が見てとれます。
※ここから先のスピーチの日本語訳は、翻訳アプリと僕の英語力を掛け合わせてつくったものです。文脈的にこういうことではないか?という感じでかなり意訳しているものもあります。間違っていたら申し訳ありません。
「The Power of Not Knowing」だと?
スピーチの冒頭の彼女の言葉に、「えっ?」となりました。
How much we know, and how we leveraged it got us far, it got us here.
But today, I wanna convince you of something counterintuitive that I’ve learned from the Class of 2024, “The Power of Not Knowing.”どれだけ多くのことを知っていて、それをどう活用したかが、
私たちを遠くまで、そしてここまで導いてくれました。
しかし今日、私は、2024年の卒業生として学んだ、直感に反すること、
「わからないことの力」についてお伝えしたいと思います。
え?と思いました。世界最高峰のハーバード大学で答辞を任されるような人が、「わからないことの力」について話すと言うのです。物事をとてもよくわかっていて、わからないことなんてないと言ってもおかしくないような人が、「わからないことに力がある」と言っているのです。俄然引き込まれつつ、ソクラテスの「無知の知」みたいなことを言いたいのかな?と思いながら見ていきました。
「わからないこと」を再定義する道のり。

クマールさんは、ネブラスカ大平原のトウモロコシ畑で南アジア(インドだと思われます)からの移民の長女として生まれ育ち、一族で初めてアメリカの大学に進学しました。願書の提出方法を両親に聞いたら「わからない」と言われたそうです。「わからない」という言葉はクマールさんにとって、無力と敗北の象徴のような言葉でした。しかしバーバード大学に進学することで、クマールさんの中で「わからない」という言葉の意味が変化していきます。
I didn’t know a field called the history of science even existed, and I now find myself a graduate of the department.
Here for the first time in my life I had a professor of color, a historian of science who taught me history is just as much about the stories we don’t know as the stories we do.科学史という学問の存在すら知らなかったのに、
今、私は、その学科の卒業生になっています。
ここで初めて、私は有色人種の教授、科学史の専門家に出会いました。
その教授は教えてくれました。
「歴史とは、私たちが知っている物語と同じように、
私たちが知らない物語も扱うものなのだ」と。
存在すら知らなかった科学史という学問と出会い、その卒業生として答辞を読むことになったクマールさん。学びたいことが明確に決まっていて大学に行く人もいれば、学びたいことが決まっておらず、学びたいことと出会うために大学に行く人もいます。クマールさんはもしかすると後者だったのかもしれませんが、このような偶然の出会いによってその後の人生が大きく変化していくことは、僕としてもよくわかります。人生はその連続とも言っても過言ではありませんよね。
そして、この教授の言葉がまた素敵です。僕は歴史を学ぶとき、人類が積み重ねてきた行為や知識を学ぶものだと思っていました。しかしこの教授は、「私たちが知らない物語を学ぶこともまた歴史である」と言っています。私たちが学校で学ぶ歴史は、基本的には記録に残っているものであり、人類が知っている事柄です。けれども記録には残っていない、膨大な物語も存在しているわけで、そういう知られざる物語があることを認識していることが大切なんだなと感じました。いやはや、自分の中の価値観をひっくり返されました。序盤のこの言葉に出会えただけでも、このスピーチを聞いてよかったと思いました。
In the history of science, we often look for what is missing, what documents are not in the archives and whose voices are not captured in history.
I’ve learned silence is rarely empty, often loud.科学史では、何が欠けているのか、アーカイブにない文書は何か、
誰の声が歴史に記録されていないのかを、よく探します。
沈黙は決して空虚なものではなく、しばしば大きな声であることを学びました。
教授の言葉通り、科学史では「歴史として記録されていないもの」をリサーチするそうです。歴史的な出来事の関係者を訪ねて取材して、知られざる事実が明らかにされる、というようなドキュメンタリー番組がよくありますが、同じような手法でリサーチしているのでしょうか。とても興味があります。この過程でクマールさんは、「知られていないこと・わかっていないことは、なかったことではない。むしろ重要なことだったりする」ということを学んでいきます。
In reflecting on our collective moments a Harvard, I’ve realized it’s the moments of uncertainty from which something greater than we could have ever imagined growth, and our class has experienced more than our fair share of the unknown.
ハーバードという集団の時間を振り返ると、
不確実な時こそ、
想像を超えた何かが成長する時なのだと気づきました。
そして私たちの代は、未知なることを少なからず経験してきました。
ここから、クマールさんの波乱に満ちた4年間の大学生活に話が展開していきます。日本でぼんやり暮らしていた僕からすると、「アメリカって、そんな大変なことになっていたのか!」と驚くことばかりです。人が生きていくうえで大切な権利が脅かされるような出来事が連発します。このように不確実な世界を生きていく中で成長していく彼女は、「わからない」という感覚を再定義していきます。「どれだけわからないか」ということに新たな力を見出すようになるのです。「不確実な時こそ、想像を超えた何かが成長する時」というのは、僕も実感としてよくわかります。自分自身を含め、自分が見てきた業界の話ですが、数年先までの自分の成長イメージが明確にあり、今やるべきことが明確に与えられている状況は、本人としてはとても楽ですが、想定内の成長にとどまりがちです。一方で、数年後の自分がどうなっているかイメージできず、そもそも今やるべきことも自分で考えて試行錯誤しなければならないような困難な状況の方が、人は想定を上回る非連続な成長を遂げるものです(もちろん途中で離脱してしまう人もいますが)。前者の方がもちろん楽で好まれる傾向が強いと思いますが、長い目で見ると、競争力の高い人材が育つのは後者の方だと思います。
クマールさんが直面した4つの不確実な出来事。
1つめの出来事は、「COVID-19」です。

日本では新型コロナウイルスという言い方の方がメジャーですね。日本の大学でも授業がオンラインになるなど、大学側、生徒側ともに大変な苦労をしましたが、アメリカでも同様に大変だったようですね。
In our first year during COVID, we didn’t have Annenberg to meet a hundred people in an hour and walk out remembering five names.
What did we do?
Cafes became the new Annenberg and we learned to connect differently building quality over quantity in our friendships.初年度には、COVID-19の影響で、
1時間で百人の仲間と出会う新入生オリエンテーションが開催されず、
5人の名前しか覚えることができませんでした。
私たちがどうしたかというと、
カフェを新たな交流の場として、
量より質で繋がるという友人関係の構築方法を学びました。
たくさんの人と対面で知り合う機会を奪われた彼女は、少数の友人と深く繋がる方法を身につけました。身につけたというより、身につけざるを得なかったのでしょうね。日本ではカフェを含むあらゆる場所でソーシャルディスタンスが徹底されましたが、アメリカのカフェはそうでもなかったのでしょうか。このあたり、詳しくなくて申し訳ありません。ちなみに「COVID-19」とは、「Corona(コロナ)」「Virus(ウイルス)」「Disease(病気)」「2019年」という4つの言葉の組み合わせだそうです。
2つめの出来事は、「ロー対ウェイド判決が覆される」です。
2022年6月24日、米国連邦最高裁は、女性の人工妊娠中絶権は合憲だとしてきた1973年のロー対ウェイド判決を覆す判決を下しました。
In our sophomore year, Roe v. Wade was overturned and there was and still is in many parts of the country, an omnipresent uncertainty in accessing reproductive healthcare.
2年生の時、ロー対ウェイド判決が覆されました。
この国の多くの地域で、性と生殖に関わる健康が不確実性にさらされています。
ロー対ウェイド判決とは、米国の多くの州でそれまで違法とされていた人工妊娠中絶について、1973年に初めて憲法上の権利として認めた判決です。合衆国憲法では中絶について明文化されていないものの、女性が中絶するかどうかを決める権利はプライバシー権に含まれるという判断でした。この裁判は、原告であるテキサス州の妊婦が「ジェーン・ロー」という仮名で呼ばれ、被告である同州のヘンリー・ウェイド地方検事と争ったことから、この名前がつきました。ローさんは訴訟当時、レイプ被害で3人目の子どもを妊娠していたそうです。この判決後も、中絶支援は「プロチョイス」と反対派「プロライフ」が米国を二分して争ってきたという経緯があります。 今回、米国連邦最高裁の判決を受けて、アメリカの各州はそれぞれ独自の州法で中絶を禁止できるようになりました。ジョー・バイデン大統領(当時)は「最高裁にとって、そしてこの国にとって悲しい日だ」と述べ、「多くの国民にとってあまりに基本的な憲法上の権利を制限するのではなく、あっさり奪い取った」と批判。さらに「中絶が禁止されている州の女性が、中絶を認める州へ移動するその基本的な権利を、私の政権は守る」と述べ、女性が移動する権利に州政府が介入することは認めない方針を示しました。トランプ大統領の共和党に政権が移り、このあたりどうなっていくのか、とても心配です。中絶が認められている日本で暮らす僕からすると、理解し難い状況です。この問題を本質的に理解するには宗教を理解する必要がありますが、僕は宗教に明るくないので、このあたりでやめておきます。
3つめの出来事は、「アファーマティブ・アクションの撤廃」です。
2023年6月29日、米国連邦最高裁は、大学の入学選考において人種を考慮するアファーマティブ・アクションを違憲とする判決を下しました。
In our junior year, Harvard faced the Supreme Court and the decision to reverse affirmative action.
3年生の時、ハーバードは、
アファーマティブ・アクションを覆すという連邦最高裁の判決に直面しました。
アファーマティブ・アクションとは、日本では「積極的差別是正措置」と訳されます。教育や雇用の機会における差別を是正するため、就職や大学入試の際に黒人やヒスパニックといった人種的少数派を優遇する措置として1960年代に導入されました。近年では組織における多様性の確保に寄与するという一方で、真に公正な入学選考を阻害するという反対派も根強く存在し、評価が割れていました。このアクションが今回、違憲(憲法違反)であるという判決になったわけです。
ハーバード大学のローレンス・バカウ学長(当時)は、「裁判所の判断に従う」とした一方で、「さまざまな背景、考え方、人生経験をもつ人々を引き続き受け入れていく」という声明を発表しました。ちなみにジョー・バイデン大統領(当時)は「強く不同意する」「この判決を結論にしてはならない。アメリカにはまだ差別が存在する」と述べました。対照的にドナルド・トランプ前大統領(当時)は「素晴らしい日になった」と称賛。「並外れた能力と成功に必要な他の全てをもつアメリカ人が、ついに報われる」と述べました。ロー対ウェイド判決もそうですが、永らくアメリカの人々の行動や価値観を規定してきた判決が覆るという、歴史の転換点にアメリカはいるのですね。
4つめの出来事は、「ドキシング」です。
ドキシング(doxing)とは、個人情報をインターネット上に不正に晒す行為のこと。アメリカの大学では、ガザ地区に侵攻したイスラエルの攻撃に対する抗議行動が広がっており、政府や実業界を含むイスラエル支持派と衝突しています。そして抗議行動に参加したハーバードの学生がドキシングの被害に遭っているとのことです。
In the fall, my name and identity alongside other black and brown students at Harvard was publicly targeted.
For many of us student of color, Doxing left our jobs uncertain, our safety uncertain.
This semester, our freedom of speech and our expressions of solidarity became punishable, leaving our graduations uncertain.秋には、黒人やブラウンの学生たちとともに、
私の名前と身元が公然と標的にされました。
多くの有色人種の学生は、
ドキシングにより仕事の不確実性や安全への不安が生じました。
そして今学期、私たちの言論の自由と連帯の表明は処罰の対象となり、
卒業は不確実なものとなりました。
SNS上での誹謗中傷は、日本だけのものではないようですね。ドキシングは特に有色人種の学生がターゲットにされ、故郷の家族が脅迫されるなど被害が拡大。ウォール街の大企業のいくつかがこの学生のリストを要求するなど、彼らのキャリアも脅かされる事態にまで発展したそうです。
As I stand before you today, I must take a moment to recognize my peers, the 13 undergraduates.
The 13 undergraduates in the Class of 2024 who will not graduate today.
I am deeply disappointed by the intolerance for freedom of speech and the right to civil disobedience on campus.今日ここに立つにあたり、
私は仲間である13人の学部生に触れなければなりません。
2024年の卒業生の中で、今日卒業を許されなかった13人の学部生たちです。
キャンパスにおける言論の自由と市民的不服従の権利に対する不寛容に、
私は深く失望しています。
さらにハーバード大学は、抗議活動に参加したことで懲罰を受けていた13人の4年生に学位授与を拒否する措置をとりました。この措置には、1,500人以上の学生と、500人近い教職員が反対の声をあげたとのことですが、残念ながら撤回されることはなかったようです。この13人の学部生たちがどのような抗議活動をして、どのような議論の末に学位授与が拒否されることになったのか、とても気になります。
Harvard, do you hear us?
Harvard, do you hear us?ハーバード、私たちの声を聞いてますか?
ハーバード、私たちの声が聞こえてるんでしょ?
アメリカ人として、ハーバードの学生として、ハーバードで起きていることは自由についての問題だとクマールさんは言います。これは市民権と民主主義の原則に関わる問題だと。1,500人以上の学生たちの声を、500人近い教職員の声を、聞いているのかハーバード?聴衆から大きな歓声が起こり、クマールさんは「言ってやったぞ」という表情で、彼女の後ろに座っている教授たちの表情にも「よくぞ言った」という感情が見てとれます。卒業生の答辞の中で学校が批判されるというインパクト。平易な言葉だけに、強く伝わりますね。2回繰り返していますが、僕には上のように異なるニュアンスに聞こえました。
私は「わからない」と言うことを選びます。
スピーチはエンディングに向かいます。「わからないことの力」とはどういうものなのか、ここから示されていきます。
I choose to say, “I don’t know.” so I’m empowered to ask to listen.
I believe an important type of learning takes place, especially in moments of uncertainty when we lean into conversations without assuming we have all the answers.私は「わからない」と言うことを選びます。
そうすることで、質問する勇気を得られるのです。
不確実な状況において、すべての答えを持っていると思わず対話に臨むとき、
私たちは重要な学びを得られると信じています。
このスピーチの中で、僕の心に一番刺さったのがこの部分でした。解決の糸口が見えない困難な状況に遭遇した時、なぜそうなっているのか、どうすれば解決できるのか、すぐにはわからないことがよくあります。その時、ネットで少し調べて「わかったということにして」スッキリしてしまうか、「わからない」ということにしてモヤモヤしながら引き続き考察を続けるか。自らを顧みると、前者をやってしまうことが多いなと反省しました。苦しくても、わからないことから逃げずに問い続けることで、問題の本質に近づいていけるのではないか。クマールさんは、不確実な状況においてこそ、「わからないことの力」が重要になると言います。民族的に標的にされることがどういうことか。暴力や死と直面することがどういうことか。それらをわからないということは一種の倫理的立場であり、共感、謙虚さ、そして学ぶ意欲のための場を生み出すのだと。「倫理的立場」という考え方は新鮮でした。「わかる」と「わからない」は優劣の関係ではなく、それぞれが価値ある立場である、ということでしょうか。
As we graduate, what we know are material knowledge may not matter so much anymore.
The truth is it’s what we don’t know and how we navigate it that will set us apart moving forward.卒業するにあたり、
私たちが持っている物質的な知識はそれほど重要ではないかもしれません。
実際には、私たちがわからないこと、そしてその中をいかに航海するかが、
私たちを前進させるのです。
ハーバードという最高学府で膨大な知識と格闘してきた人だからこそ、そして多くの不確実な出来事を体験してきた人だからこその、説得力を感じます。不確実性は不快だが、不快感の中に飛び込むこと。初心、つまりわからないことの倫理を持ち続けることを勧めるクマールさんでした。
Emily Dickinson had said, “Not knowing when the dawn will come, I open every door.”
Thank you, and congratulations.エミリー・ディキンソンはこう言いました。
「夜明けがいつ来るかわからないけれど、私はすべてのドアを開けておく」と。
ご清聴ありがとうございました。
そしておめでとうございます。
スピーチの締めに、こういう名言をもってくるところがニクいですね。スピーチのテーマにぴったりで、なんともオシャレです。「The Power of Not Knowing」と言っておきながら、最後の最後に知の力を披露する感じも、爽やかな読後感をもたらしてくれました。エミリー・ディキンソンは、アメリカの詩人です。生前は無名でしたが、1,700篇以上残した作品は世界中で高い評価を受けており、19世紀世界文学史上の天才詩人のひとりとされています。
「The Power of Not Knowing」の適切な日本語訳は?
「The Power of Not Knowing」は、直訳すると「知らないことの力」です。このスピーチを取り上げたブログ等の文章の多くも、そのように訳しているようですが、僕は「知らないことの力」では、わかるようで、わからないと思いました。これだとクマールさんがスピーチに込めたニュアンスが伝わり切らないなと。「The Power of Not Knowing」の適切な日本語訳が「わからない」というモヤモヤ状態をキープしながら考え続けること1週間あまり。「The Power of Not Knowing:わからないことを自覚することによって生まれる力」がニュアンス的に近いかなと思うに至りました。一旦、こうしておきますが、もっといい答えがあるような気がするので、引き続き考えたいと思っています。「わからない」は続きます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。クマールさんのインスタグラムはこちらです。ご興味のある方はアクセスしてみてください。このような天才的なスピーチはなかなかマネできませんが、スピーチ原稿は基本的な考え方とスキルを身につければ、誰でも書くことができます。よろしければ、スピーチ原稿を書く僕を助けてくれる本5冊。もあわせてお読みください。あなたの人生にとって少しでもプラスになる情報をお届けできたらうれしいです。ではまた。